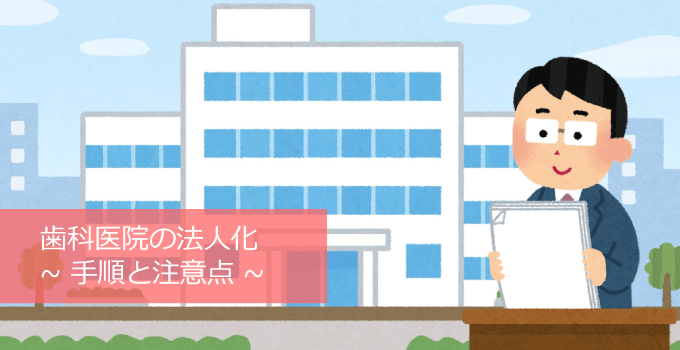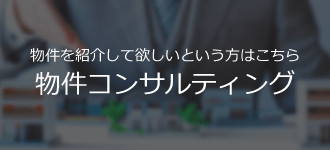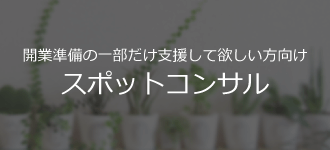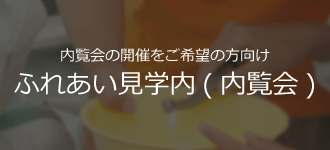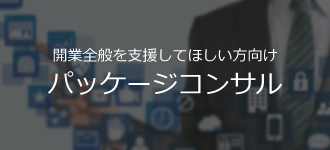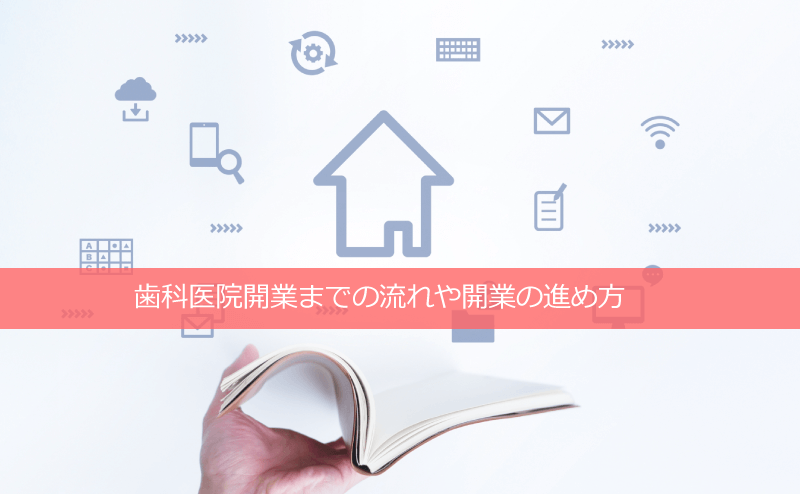「歯科医院の医療法人メリット・デメリット」では、法人を設立するかどうかについてまとめましたが、今回は法人設立の手順と注意点についてお話しします。
医療法人の種類と業務範囲
はじめに、医療法人の基礎知識をおさえておきましょう。医療法人は医療法第三十九条で定められており、
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
前項の規定による法人は、医療法人と称する。
医療法第三十九条
と定義されています。
条文にもある通り、医療法人は社団医療法人と財団医療法人の二つに大別でき、実体により区分されています。人の集まりが社団、財産の集まりが財団です。
医療法人には業務範囲に規定があり、本来業務・附帯業務・附随業務に分けてすべき業務が決められています。
この内、都道府県知事の認可が必要なものは本来業務と附帯業務で、本来業務は診療所や介護施設の運営そのものを指し、附帯業務には教育や研究所の設置、衛生や介護事業、患者の送迎などがあり、附随業務を行うためには定款(財団の場合、寄附行為)の変更手続きを行って、都道府県知事から承認を貰う必要があります。
詳しくは厚生労働省の発行している「医療法人の業務範囲」をご確認下さい。そのほか、特殊な法人がいくつかあるのでご紹介します。
一人医師医療法人
医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1箇所開設しようとする社団又は財団の医療法人のこと
さいたま市「医療法人設立認可申請書類一覧」注釈14補足
と定義されているように、通常は3名以上の役員構成を要件として法人の認可を受ける事ができますが、これを1人からでも認めるとしたものが一人医師医療法人です。
昭和60年の医療法改正(医療法 第四十六条の五)から適用され、以後個人開業医の法人化が急速に進み、平令和4年では医療法人数57,141件に対し一人医師医療法人は47,295件と、およそ約83%のシェアを占めています。
社会医療法人
定款(または寄附行為)で定めれば、本来業務に支障をきたさない範囲で、病院・診療所・介護老人保健施設を経営に充てることを目的とした収益業務を行うことができる法人です。
医療保険業の法人税などが免除されるなどのメリットがありますが、制約があり、同族経営の制限、一定の救急医療提供が必要、出資持分や残余財産の請求権がなくなるなどといった条件が課されます。
特定医療法人
財団又は持分の定めのない社団の医療法人
抜粋:厚生労働省「特定医療法人制度について」
国税庁長官の承認を受ければ19%の軽減税率が適用されますが、同族経営やその利益、役員報酬、保険診療収入、自費請求額についてなど各種制限があります。
歯科医院の法人化手順
医療法人としての申請を行うには、定められたいくつかの要件を満たす必要があります。まずは条件を確認し、綿密に準備を整えましょう。
医療法人設立の要件
医療法人設立には、人的要件・財産的要件があります。
人的要件
・社員 原則3名以上
・理事 原則3名以上(社員から選出・自然人である事が条件)※
・監事1名以上
・理事のうち医師または歯科医師の1人を理事長に選任
※特例:一人医師医療法人
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
医療法 第四十六条の五
財産的要件
・拠出(寄附)財産
不動産
建物付属設備
現預金
医業未収入金…直近2か月分
医療用器械備品
什器・備品
電話加入権
保証金等
・運転資金:初年度の年間に支出する予算の2か月分
・負債:拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、法人が引き継ぐことができる
(ただし、借入日より後に支払を行っていること)
より詳細は、厚生労働省「医療法人設立の手引」をご参考下さい。
医療法人設立時の注意点
拠出資金の内訳
法人化にあたり資金を拠出する際、個人事業時代に借入していた運転資金をそのまま法人へ拠出する事は難しく、個人の借入資金として残ってしまいます。その為、法人化した時の給与設定を返済分も上乗せした設定にするなどの配慮が必要な場合があります。
人的要件の配置
法人化すると社員が理事決定権を持ち、社員総会で一人1議決権を持って理事決定を行うので、場合によっては法人を立ち上げた自身が理事に任命されない場合もあり得ます。第三者の社員を多くするとその様なリスクが高くなる事を念頭に置き、採用や配属管理に留意しましょう。
また、監事は六親等内の親族など近しい人を置く事は禁じられており、第三者に委ねる必要があります。決算書の押印や運営への指導など、権限を持つ役職になるので、信頼できる方にお願いしましょう。実際は懇意にしており信頼できる歯科医師や税理士に頼むケースが多い様です。
決算月の設定
決算月については法人設立時に決めておく必要がありますが、最適な月に設定しておかないと免税期間が殆どなく、すぐに課税対象事業者と見做され税金の支払いが生じるケースもよく見受けられます。法人化による消費税・所得税上の節税のメリットをよく考え、自身の法人設立に応じ適切な設定を行いましょう。
医療法人設立の流れ
東京都の場合を例にとって考えてみましょう。
※各種機関の対応内容は、管轄により多少変動します。自分が法人設立をする所轄期間の条件を必ず事前にチェックして下さい。
東京都で法人を設立する場合
5ヶ月前頃
- 定款・寄附行為(案)の作成 ※1
- 設立総会の開催
- 設立認可申請書の作成
※1:東京都福祉保健局では「医療法人設立の手引」があります。準備前、認可受領後の適切な時期に資料を手に入れ、内容を把握しておきましょう。
4ヶ月前頃
- 設立認可申請書の提出(仮受付)※実質的な申請行為→提出先:東京都
- 設立認可申請書の審査 (保健所等の関係機関への照会、面接等含む)
~審査結果、この時点で「取下げ」の場合もあり~
- 設立認可申請書の本申請→提出先:東京都
- 医療審議会への諮問
- 答申
- 設立認可書交付(受領)※1
3ヶ月前頃
- 設立登記申請書類の作成・申請→提出先:地方法務局(登記所)
- 登記届→提出先:東京都
~登記完了(法人成立)~
前月10日頃 ※2
- 診療所の開設許可申請→提出先:所管の保健所
- 診療所の開設許可(許可書受領)→提出先:所管の保健所
※2:保険診療を始める時に必要な保険医療機関指定申請書については、都道府県ごとに締切日の設定があるので、厚生局のホームページで必ず期限をご確認下さい。
開業後10日以内
- 個人開設:診療所の廃止届 ※開設届と同時提出
- 個人開設:エックス線装置廃止届
- 個人開設:保健医療機関廃止届
- 医療法人:診療所の開設届
- 医療法人:エックス線装置設置届
- 医療法人:保健医療機関指定申請書
→提出先:所管の保健所(廃止・開設後10日以内)
設立の流れはおよそ5ヶ月前からのスケジュールで簡単にまとめてありますが、実際にはこれらの書類準備に更に最低3~4ヶ月は必要となるので、意思決定や顧問税理士・コンサルティングの方へのご相談などは早めに動く様に心がけましょう。
一般的には春・秋の年2回に分け申請を受付けていますが、都道府県により日程や年間の受付回数が異なるので、管轄の自治体の情報を必ず確認して下さい。
インサイトでは、法人後の分院展開をご検討中の先生向けの開業支援サービスも用意しております。詳しくは、インサイトの開業支援コンサルティングサービスをご覧ください。
いつ頃までに法人化させ、分院を出すのか?先生のご予定に合わせたサポートを行いますのでお気軽にご相談ください。
- 歯科医院分院展開のポイント
- 歯科医院の分院展の手順と体験談~分院展開の道のり~
- 分院長になる時・分院長を探す時のそれぞれの注意点
- 歯科の管理者になったらすることとよくある質問
- 歯科医院法人化のメリット・デメリット
- ユニット増設はいつ?増設目安とタイミング
- 歯科医院の移転を考えたら?移転前に決めておくべき6つのこと
- 歯科医院をリフォームする時の注意点とは?
- 歯科の増床!ビル内別フロアで増床する3つのメリットと注意点
- 歯科医院が一般社団法人に転換する4つのメリットと留意点