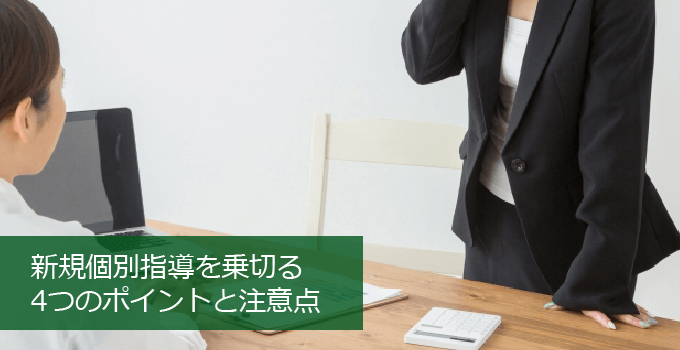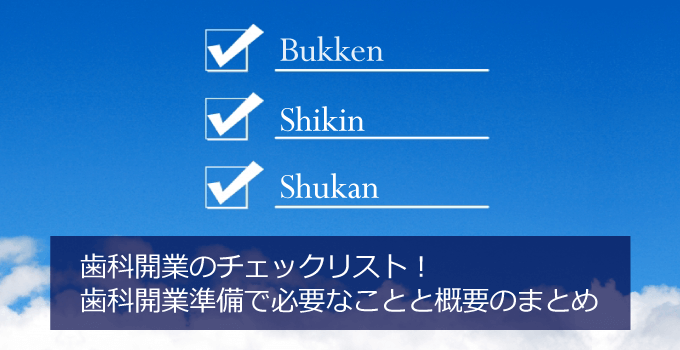開業した全ての医療機関に対し新規個別指導が行われますが、歯科も例外ではありません。
以前「新規指導の仕組み解説」で簡単な流れをお話しましたが、今回は、実際にどのような事をよく聞かれるのか、それらの質疑にどう対応していったらいいのかを4つのポイントに絞ってご説明します。
帳票の整合性は取れているか
カルテ=技工指示書=納品伝票になっているか?
皆さん、技工物などの納品伝票は全て保管しているでしょうか?納品があった時、物品と帳票の内容が合っていれば伝票は捨ててしまう事も多く、開業後数ヶ月もすると指示書に対応する納品伝票が見つからないというような事が現場では往々にしてあるようです。
他にも、保険適用内で技工指示書を出したものの制作工程で自費込みの技工物が仕上がり、歯科医師も患者さんも納得の上でその技工物を治療で使用したが、当初出した指示書やカルテの修正が漏れてしまった…などという場合には、各帳票の内容に差異が生まれます。
これらのように不足や違いがあれば新規指導の場でどういう事か問われるので、帳票同士で相違がないように気をつけましょう。
患者ごとの日計表
日計表は手書き、パソコンで打ち出した表、どちらを持参しても構いませんが、カルテ内容と差異がないかどうかをチェックされます。簡単な数字合わせではありますが、日ごろからきちんと管理しておきましょう。
予約帳=カルテになっているか?
予約帳に名前があるのに、対象の患者さんのカルテが存在しない…などといった差異があると、詳細を尋ねられます。
実地指導の記録簿
実地指導の指導や処置を行った場合には、担当の歯科衛生士が書いた記録が必要になります。これは実地指導の算定の有無に関わらず必要です。この記録については書いていない事も多く、いざ新規指導となってから慌てて揃えるクリニックも少なくありません。
まとめて書くと同じ内容になりがちですが、同じ内容があまりにも多いとそれも査問の対象となるので注意しましょう。
診療処置は妥当なものだったか
カルテをきちんと書いているか?
何の為にどのような治療計画を立て、どのような検査・処置を行ったかという筋道だったカルテ記載が必要です。必然的に1つあたり数行は記載する事になるかと思いますが、あまりに少ない文面だと内容が伝わり難く、注意されるので気をつけましょう。
歯周治療の期間
SC終了後、2回目の検査に進むにはおおよそ1週間以上の期間が必要になります。その後、SRPを行った後は次の検査まで更に約2週間以上の期間を空ける必要があります。
あまりに短い期間内で行っていると注意されるので気をつけましょう。これらの期間について公的機関から具体的な通知などは出ていませんが、診療の観点からそのくらいが妥当と判断されます。
パノラマ撮影
点数が高いこともあり、本当に撮る必要があったかどうかをチェックされます。撮影理由や診断コメントをきちんと記載し、指導官から理由を聞かれても必要性を説明できるようにしておきましょう。
誰が行うべき作業なのか、責任の切り分けはできているか
カルテの記載は誰が行っているか?
こう聞かれた時、バイトや助手が行っていると回答するのはNGです。カルテはドクターが記載すべきものなので、そのように実践し答えましょう。
未収金の対処
患者が診療費を支払わない場合、どのような取り組みをしているか聞かれる事があります。保険診療の患者負担3割の回収についてはクリニックの責任になりますので、自医院で対処している内容を答えましょう。
日頃の整理整頓はできているか?
患者への交付文書の写し
患者への提供文書は写しをカルテに挟む決まりですが、この写しをカルテに添付していない事が意外と多くあります。必要事項の記載はもちろん、打ち出してカルテに挟むまでが必要になるので気をつけましょう。後から一括して出すとなると、年度をまたいで様式が変わる事もありとても大変な作業になるので、都度出力しファイルしておきましょう。
口腔内写真の添付
口腔内写真はカルテに添付する義務がありますが、歯科用デジカメがレセコンと連動しておらず、別の端末にデータが入っていたりする事もあります。
いざ提出となった時、カルテに添付してないばかりかデータの所在も良くわからない、などという事もよくありますので、こちらも日ごろから気をつけましょう。
歯科の新規個別指導についてでした。歯科開業トピックスでは、他にも以下の様なコンテンツを配信しています。
インサイトの『一括デモサービス』